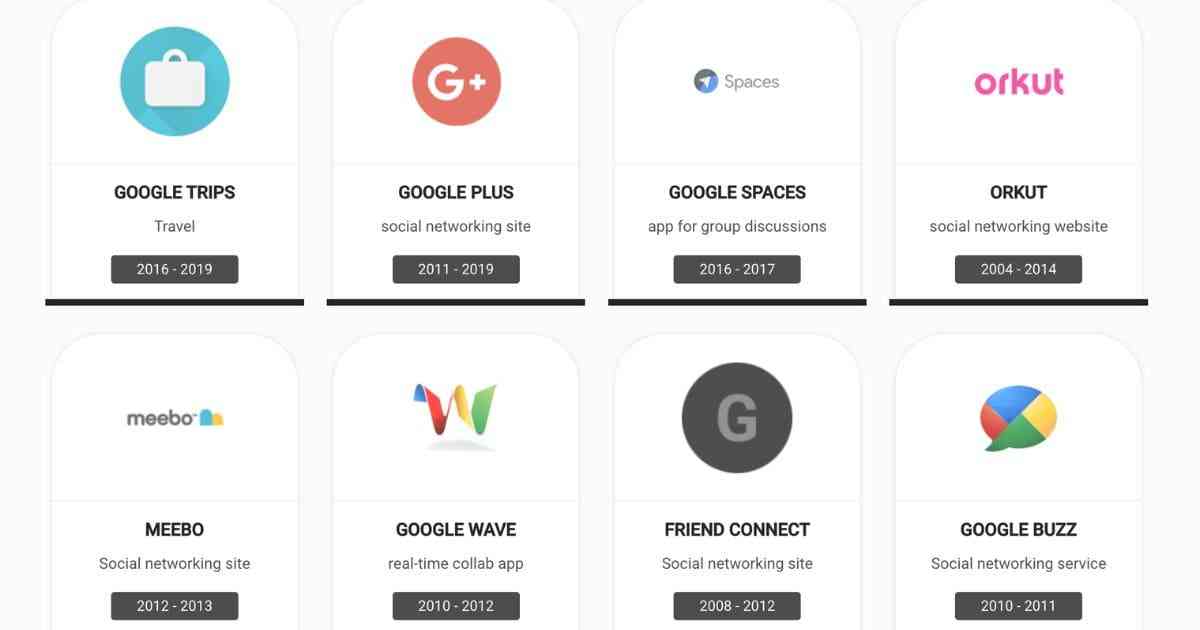大企業、特に当時のシリコンバレーに象徴される「成功神話」を持つ企業について語る際、批判的な論調は注目を集めやすい傾向があります。
しかしここで取り上げたいのは批判ではなく、かつてGoogleに存在していた「独自の企業文化」についてです。
その文化は現在も他の企業にとって学びの対象になり得ると考えられます。
Googleの創業初期、とりわけ最初の10年間は、「社員こそ最も重要な資産である」という考えが実際の経営・運営に反映されていました。
一般的な米国企業では、プロジェクトの終了とともに関係者が解雇されることが多い一方で、当時のGoogleは長い時間をかけて採用した「優秀で汎用性のある人材」を解雇せず、他部署へ再配置する仕組みを持っていました。
「製品は変わっても、社員は変わらない」という姿勢が共有されていたのです。
この文化のもと、部門再編の際には社員一人ひとりの適性に基づいて配置転換が行われ、心理的安全性や仕事への満足度を高める要因となっていました。
実際、再配置後に新しい職務を楽しんでいると感謝の言葉を寄せる社員もいたといいます。
しかし、時代の変化とともに状況は変わりました。
ある社員が「収益の成長が止まった瞬間に文化は変わる」と予測していたように、パンデミック以降の売上鈍化を境に、企業文化は「有限資源を前提とする」方向へ移行していきました。
具体的には、福利厚生の縮小、採用や昇進制度の変化、さらには大規模なレイオフが行われました。
かつてのように社員を守るための個別対応は難しくなり、一般的な大企業と同様に「旧プロジェクトからの解雇 → 新プロジェクトでの採用」という流れが定着しつつあります。
これは決してGoogleを否定するものではなく、上場企業として財務責任を果たすうえで自然な変化ともいえます。
ただ、初期に見られた「社員を最優先にする文化」をどのように維持できるのかは、依然として企業経営における大きな課題です。
この事例から得られる示唆は明確です。
社員が大切にされていると実感できる環境は、心理的安全性を育み、士気・生産性・創造性を高めます。逆に、リストラの恐怖がある状況では「失敗を恐れず挑戦する文化」を育むことは難しいでしょう。
企業を成長させたいと考える経営者にとって、最も重要な資産と捉える姿勢は依然として有効な戦略であり、長期的に大きな成果をもたらす可能性があります。
※本稿は、ベン・コリンズが18年間Googleで働いた経験を元に記載しています。経営陣の正式な意図を代弁するものではありません。